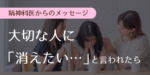こんにちは。国語教師の常田です。
末摘花や空蝉は、光源氏を取り巻く女君の中では端役ですが、それぞれ、中心人物として描かれる巻が、2巻あります。
「そこまで彼女たちを描く必要があるのかな?」という人もあります。なぜだったのでしょうか、皆さん考えてみてくださいね。
今回は、「蓬生の巻」「関屋の巻」のあらすじを解説します。
蓬生の巻:あばら屋で待ちわびる
光源氏が須磨や明石にいた頃、末摘花(すえつむはな)の生活は窮乏を極めていました。
末摘花は、源氏が18歳の頃に出逢った、鼻が象のようで、先が紅い、という女人です。
光源氏は、関わりを持った女性を見捨てることは、決してありません。いわゆるプレイボーイとは違います。
しかし、末摘花のことは忙しさのあまり、忘れてしまっていました…。
末摘花の世話をする人はおらず、庭は蓬(よもぎ)やむぐらが、生い茂るがままになっています。
女房たちも貧しい生活に耐えかねて、次々と去っていきました。
しかし、彼女は亡き両親の面影を慕い、家財道具を手離そうともせず、光源氏が必ずまた訪ねてくれると信じて、荒れた邸を守っていました。
ある時、明石から都に戻った光源氏が、あばら屋になった御殿の側を通りかかりました。
見覚えのある邸に、やっと末摘花を思い出した光源氏は、まだ彼女が住んでいるのだろうか、と訪ねます。
末摘花にすれば、待ちわびていた光源氏が、やっと訪ねてきてくれたのです!
言葉にならぬ嬉しい気持ちだったでしょう。ただそれもあってか、例によってなかなか返事ができません。
光源氏は、
藤波の うち過ぎがたく見えつるは 松こそ宿の しるしなりけれ
(松にかかる藤の花を通り過ぎがたく思ったのは、松に覚えがあったからです。あなたが変わらずに待ってくれている、それが思われたからでした)
と詠みかけます。
末摘花は、昔より落ち着いて女らしくなっていました。
光源氏は、自分を一途に待っていた末摘花に心打たれます。
無位無官になって、須磨や明石でさすらっていた時、自分に恩義がありながら背を向けていった者は多くありました。
「こんなに貧しくなっても、自分を信じて待ち続けてくれる人がいたとは…」
光源氏の人間に対する眼差しは、内面にも向けられるようになっていました。
関屋の巻:女君への心づくし
源氏はこの後、末摘花邸の修理をし、彼女の生活の面倒を見るようになります。
そして2年後には、自邸の一つに引き取りました。
ところで光源氏が17歳の頃、中流層の女人に関心を持って、強引に逢瀬を遂げた空蝉(うつせみ)は、夫とともに常陸国に下っていました。
しかしその後、光源氏が明石から帰京した翌年の秋に、空蝉も、夫と都に帰ってきたのです。
そしてなんとその時、逢坂の関で、石山に向かう光源氏一行と出会ったのです。
光源氏は空蝉に対してさまざまな思いが浮かびますが、直に会うことはできません。
空蝉も昔を思い出して、せつない気持ちでした。
光源氏は一筆書いて、彼女に文をやります。
空蝉は独り歌を詠みました。
行くと来と せきとめがたき 涙をや 絶えぬ清水と 人は見るらん
(逢坂の関を越えて行く者と来る者と、すれ違って別れていく。それを悲しんでとめどもなく流す私の涙を、絶えず流れる関の清水と人は見るのであろうか)
その後、空蝉の夫は、息子たちに空蝉を母として大切にするよう遺言して、亡くなりました。
しかし空蝉は、年上の継子に言い寄られ、生活の見通しもないまま出家してしまいます。
光源氏はその後、空蝉をも自邸の一つに引き取って、面倒を見たのでした。
******
※「蓬生」(よもぎう)という巻名は、末摘花の荒廃した邸に茂る蓬に因んでいる。
源氏物語全体のあらすじはこちら
源氏物語の全体像が知りたいという方は、こちらの記事をお読みください。
話題の古典、『歎異抄』
先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。
令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。
ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!