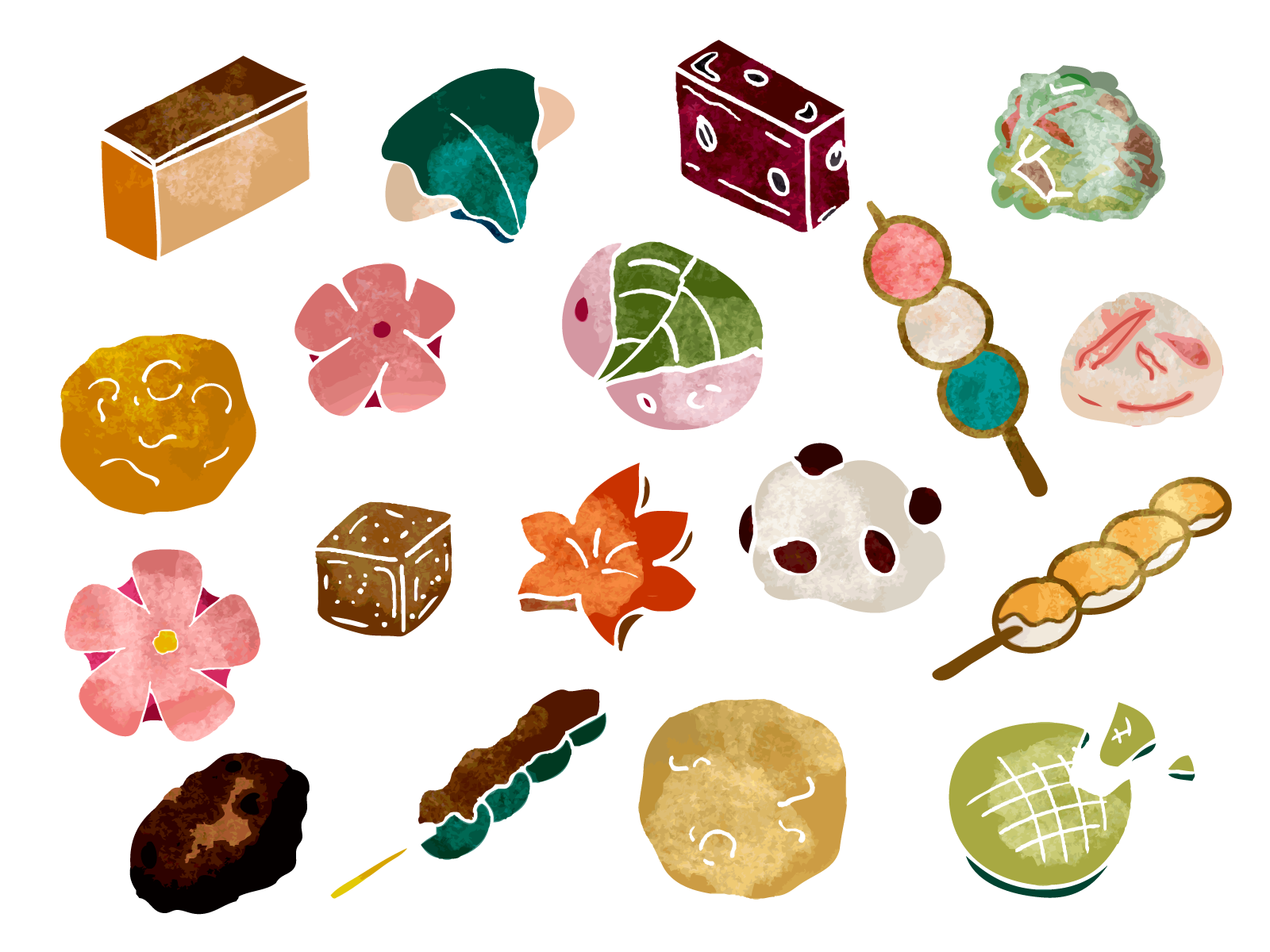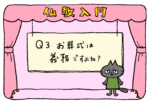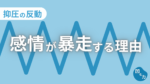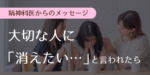こんにちは。国語教師の常田です。
よく似た経験を持つ年配の方が、悲痛な思いが甦ると言われるところです。
光源氏ももう三十路に入りました。政界の重鎮となり、正妻格の紫の上と暮らしています。
もう一人の妻・明石の君も、都に近い大堰(おおい)という所に住んでいました。姫は3歳になり、かわいい盛りです。源氏は紫の上の機嫌をうかがいつつ、月に数回は大堰を訪れていました。
そんな源氏31歳の冬の頃の話です。
「薄雲の巻」のあらすじを解説します。
明石の君の生きがい・愛する娘との別れ
明石の君は、源氏から幾度となく都への移住を勧められますが、かたくなに拒んでいました。
田舎育ちで身分の低い自分が、都の大貴族たちと暮らすのは肩身が狭いと思うからです。
すると今度は、「姫だけでも都に迎え、紫の上の養女にしたい」と切りだされました。
姫の将来と一族の繁栄を考えてのことでしょう。
“ああ、やはり…。”
源氏のそんな思惑は前々から察していた明石の君ですが、娘は唯一の生き甲斐、希望です。胸が潰れそうでした。
さらに姫を手離せば、源氏は逢いにこなくなる予感もあります。
しかし、明石の君の母は、考えが違いました。
「子どもの人生は、母親の身分で大きく左右されるのですよ。姫をこんな片田舎に埋もれさせていいのですか。身分の高い紫の上の養女にして、栄えある人生にしてやりなさい」
と諄々と説得しました。
こうして明石の君は、
「放ちきこえんことは、なおいとあわれにおぼゆれど、君の御ためによかるべきことをこそは」(手離すのはやはりとてもつらいけれども、姫の幸せを第一に考えねば)
と娘を手離すことに同意しました。
人生にはさまざまな苦難がありますが、愛するものと引き裂かれる悲しみは、いかばかりでしょうか…。
雪や霰の散らつく日が多い頃でした。
心細さがつのる明石の君は、いつも以上に娘の髪をなでながら、「なぜかあれこれと物思いをしなければならない身の上なのね」と深く嘆かざるをえません。
紫の上の養女となった我が子
雪が少し解けた頃、源氏が姫を迎えに来ました。今更ながら明石の君は、娘を手離すことを悔やみます。
“でも今になって渡せないと言えば、軽々しい女と思われるだけ”と自分に言い聞かせ、思いとどまりました。
車を寄せた所に、乳母ではなく、明石の君が自ら姫を抱いて出ていきました。
急いで車に乗ろうとする無邪気な姫。
可愛らしい声でたどたどしく、
「お乗りなさいよ」
と母親の袖を引っ張ります。
堪えかねてすすり泣く明石の君は、源氏にこんな歌を詠みました。
末遠き ふたばの松に ひきわかれ いつか木だかき かげを見るべき
(行く末遠い、双葉の松のような幼子と別れて、いつ立派に成人した姿を見ることができるでしょう)
姫を乗せた車は、ゆっくりと遠ざかっていくのでした。
車の中で眠ってしまった姫は、源氏の邸に到着してからも、しばらくは機嫌よく菓子を食べていましたが、やがて周囲を見渡して、しくしく泣き出してしまいます。
母の姿がどこにもなかったからです。
しかし、あまり人見知りをしない性格もあってか、姫は紫の上にすぐなつき、新しい生活に馴染んでいきました。
明石の君は、姫が大切に養育されている様子を聞くたび、ほっと胸をなで下ろします。
一方で、別れを後悔する気持ちも依然としてありました。
寝ても覚めても娘の面影が浮かび、一時も心から離れないのでした。
******
※「薄雲の巻」の由来は、「入り日さす峰にたなびく薄雲はもの思ふ袖に色やまがへる」という光源氏が詠んだ和歌からきている。
源氏物語全体のあらすじはこちら
源氏物語の全体像が知りたいという方は、こちらの記事をお読みください。
話題の古典、『歎異抄』
先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。
令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。
ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!