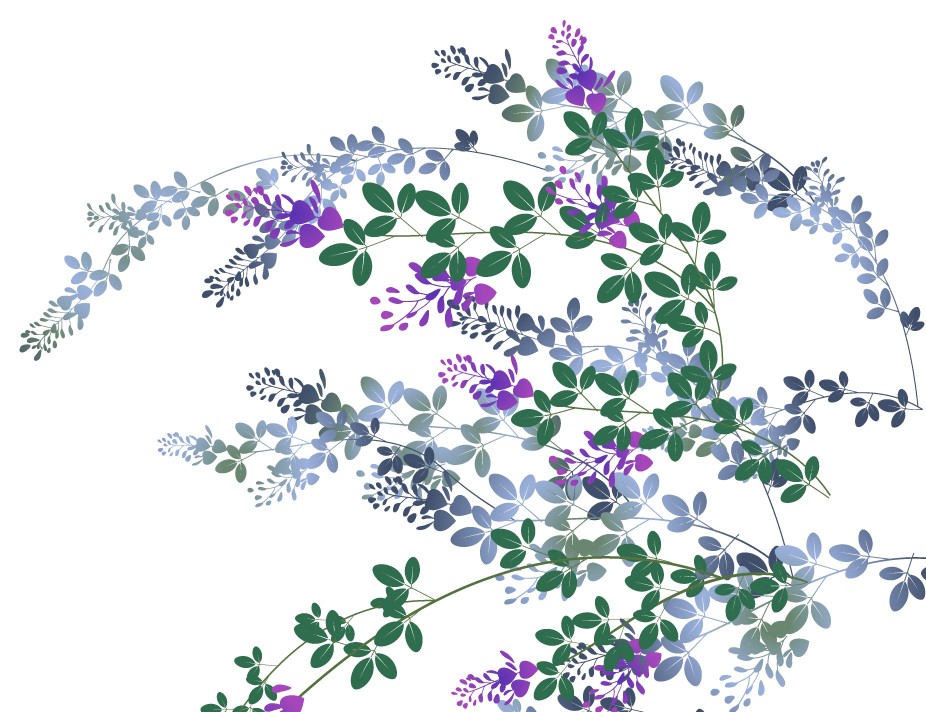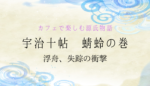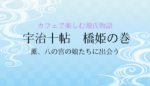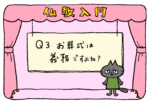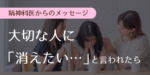光源氏の孫・匂の宮
夏になり、暑さのためか、紫の上は一層衰弱し、しばしば意識を失うこともありました。
明石の中宮が、二条院の紫の上の元を訪れました。
源氏と明石の君の実子で、紫の上の養女として育てられた女性です。
今は帝の后となって宮中におり、自由に会うことも叶いません。
思いがけぬ、うれしい訪問に、紫の上は体を起こし、あれこれと語り始めるのでした。
そして、
「孫たちの成長を見届けたい、と思っていたのは、はかないわが命を惜しむ心からでしょうね」
と涙ぐみます。
5歳になる孫の匂の宮には、「私がいなくなっても思い出してくれますか」と尋ねます。
目をこすりながら匂の宮は「とっても恋しいと思います。僕はおばあさまが大好きだもの」と答えます。
「大人になったらここで暮らしなさい。春には紅梅や桜をめで、仏さまにお供えするのですよ」
そのまなざしには、孫の幸せを念ずる温かさと、行く末を見届けられない無念さが入り交じっていました。
紫の上の遺言にこくりとうなずいた匂の宮は、泣き顔を見られるのが恥ずかしいのか、隣の部屋へ行ってしまいました。
この匂の宮が、『源氏物語』後半で、中心的役割を果たします。
露が消えるように…。紫の上の最期
季節は移ろい、涼しくなりました。
紫の上の体は更に衰弱していきます。
夏以降も引き続き、二条院で紫の上に付き添う明石の中宮の元に、宮中から頻繁に使者がやってきて、帰るよう促します。
帝や中宮は、たとえ肉親でも、重病人や死者に接してはならない、というしきたりがあるためです。
口には出しませんが、紫の上は、”もう少しそばにいてほしい…”と思っていましたし、中宮も宮中には戻る気はなく、最期まで付き添う覚悟でいるようでした。
風が激しく吹きだしたある秋の夕暮れ、紫の上は少し気分がよいのか、脇息に寄りかかって風に当たり、庭で揺れる草花を眺めていました。
自分が少し身を起こしただけでも大喜びの源氏を見て、”私が死んだら、どれほど苦しまれることか…”と悲しい気持ちになりながら、源氏と歌を詠み交わします。
おくと見る ほどぞはかなき ともすれば 風にみだるる 萩のうわ露
(萩の上の露が、見る間もないほどすぐに風に乱れてしまうがごとく、今はこうして私が起きているのを見ていても、もはやはかない命、すぐに消えてしまうことでしょう)
ややもせば 消えをあらそう 露の世に おくれ先立つ ほど経ずもがな
(どうかすると先を争って消えていく露のようにはかない世では、先立ったり遺されたりする間をおかず、一緒に消えてしまいたいものです)
間もなく紫の上は気分が悪くなり、「見苦しい姿をお見せするのはちょっと…」と源氏に退室を促して、伏してしまいます。
そしてそのまま夜が明けて、露が消えるように、紫の上は静かに息を引き取ったのでした。
永遠に、の願いはかなわず
「かくて千年を過ぐすわざもがな」と思さるれど、心にかなわぬことなれば、かけとめん方なきぞ悲しかりける。
(光源氏は、最愛の妻・紫の上と「このまま永遠に過ごせるすべがあれば…」と思うけれども、消えゆく命を引き止める道のないのが、何とも悲しいことであった)
いつまでも永遠に共に過ごしたい、という願いも叶わず、光源氏は最愛の女性を失いました。
栄華を極め、権勢を誇っていても、愛別離苦からは免れられませんでした。
「紫の上を出家させてやろうと思う」
彼女の亡骸を前に源氏は、長男・夕霧に儀式の準備を命じました。
しかし、「亡くなった人を形だけ出家させても、甲斐のないことですよ…」と逆になだめられるのでした。
*******
- 二条院:紫の上が静養していた光源氏の別宅。本宅の六条院を建てるまで源氏と紫の上はここで暮らしていた。
- 中宮:帝の妃のトップ
- 脇息:ひじ掛け
源氏物語全体のあらすじはこちら
源氏物語の全体像が知りたいという方は、こちらの記事をお読みください。
前の記事を読む 次の記事を読む これまでの連載はコチラ
※イラストは tatsukimegさん
話題の古典、『歎異抄』
先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。
令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。
ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!