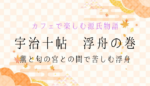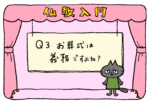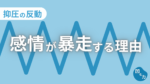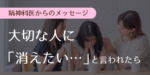紫の上が残した花木
盛りの梅を光源氏が眺めて詠んだ歌です。
植えて見し 花のあるじも なき宿に 知らず顔にて 来いるうぐいす
(梅の木を植えて花を楽しんでいた主人〈妻・紫の上〉もいない宿に、うぐいすは、そんなことも知らぬ顔でやって来て鳴いているよ)
光源氏52歳。1月、2月と時は流れ、紅梅が盛りを迎えました。
源氏と一緒に暮らす6歳の孫・匂の宮が、
「おばあさまが仰ったことだから」
と紅梅の世話をして回るのを、源氏はしみじみと見つめます。
紫の上は生前、最もかわいがっていたこの匂の宮に、
「春になったら私を思い出し、ここにある紅梅や桜をめでて、仏さまにお供えするのですよ」
と遺言していたのです。
春が好きだった紫の上は、開花時期が少しずつ違う花木を何種類も庭に植え、大切に育てていました。
今年も梅に続き、桜が開きました。
「まろが桜は咲きにけり。いかで久しく散らさじ」
(ぼくの桜がきれいに咲いたよ。何とかしていつまでも散らさずにおきたいな)
と幼いなりに、”無常を食い止める”方法を匂の宮は一生懸命に考えます。
「桜の木を几帳で囲めば、風が吹き込まないぞ」
名案を思いついた、と得意気な孫の姿に、源氏も思わず笑みがこぼれました。
そしてすぐに、「こうしてあなたと過ごすのも、あとわずかだ」と涙ぐみます。
梅も桜も見納め、山奥に入って仏道一筋に求めたい、という気持ちからでした。
忘れられない紫の上の面影
春のつれづれ、源氏は数年前に出家した正妻の女三の宮を訪ねました。
日々、心静かに勤行に励む彼女は、悲しみに思い乱れる源氏とは対照的です。
源氏は慰めてほしくて世間話を始めますが、女三の宮の返事に、彼の心を察する配慮は感じられません。
彼女に悪気はないのでしょうが、源氏はひどく傷つきました。
その足で明石の君も訪ねます。
聡明な彼女との語らいで少しは心が安らぎましたが、つい紫の上の面影が浮かび、寂しさもつのるのでした。
初夏、衣替えの時季となりました。
正妻が夫の夏服を新調するのが当時の習わしです。
紫の上に代わり、今年は花散里が仕立てました。
源氏は返礼の文に、こんな一首を読みました。
羽衣の うすきにかわる 今日よりは うつせみの世ぞ いとど悲しき
(薄い夏衣に替わる今日からは、空しいこの世がますます悲しく思われることでしょう)
「紫の上はどこへ…」雁に問う光源氏
五月雨の夜には長男の夕霧が訪ねてきます。
親子ですから、夕霧には、源氏が何を話していても紫の上のことしか考えられないのが手に取るように分かり、いたわしい思いになるのでした。
夏の盛りには、池の蓮を眺め、気が抜けたように日暮れまで過ごした日もありました。
ひぐらしの鳴き声が響きわたり、撫子が夕明かりに浮かび、蛍が飛び交う。
そんな自然の美も、独りで眺めても張り合いがありません。
ふと源氏の脳裏に浮かぶ古歌は、妻の無常を嘆くものばかりでした。
初秋の風が身にしみる頃、紫の上の一周忌を迎えました。
「今日までよくも生きてきたことよ」と感慨深くつぶやく源氏も、さすがに法事の準備で少しは気が紛れたようでした。
しかし、秋が深まり時雨がちになると、一層物思いに沈みます。
空を渡る雁をじっと見つめ、
「夢にだに見えこぬ魂の行く方たずねよ」
(夢にさえ姿を見せない紫の上は、どこに行ったのか、捜しておくれ)
と痛切に問わずにおれません。
今までの人生、栄華も苦悩も、仏さまのお導きであったと知らされ、わずかな余命を仏法にかけねばと思いつつも、いまだ一歩が踏み出せぬ光源氏…。
春、夏、秋と時は流れ、悲しみは癒えるどころか、深まるばかりのようでした。
こうして冬を迎えます。
*******
- 1月、2月:旧暦では1月から3月が春
- 几帳:T字の柱に薄絹を垂らした間仕切り
- 女三の宮:光源氏が40歳で結婚した正妻。この時は出家していた
- 明石の君:源氏の妻の1人。源氏の大邸宅・六条院の冬の町で暮らす。かつて紫の上は、源氏の娘を産んだ彼女に対抗心を燃やしていた
- 花散里:源氏の妻の1人。六条院の夏の町で暮らす
源氏物語全体のあらすじはこちら
源氏物語の全体像が知りたいという方は、こちらの記事をお読みください。
前の記事を読む 次の記事を読む これまでの連載はコチラ
イラスト:このはなさん
話題の古典、『歎異抄』
先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。
令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。
ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!