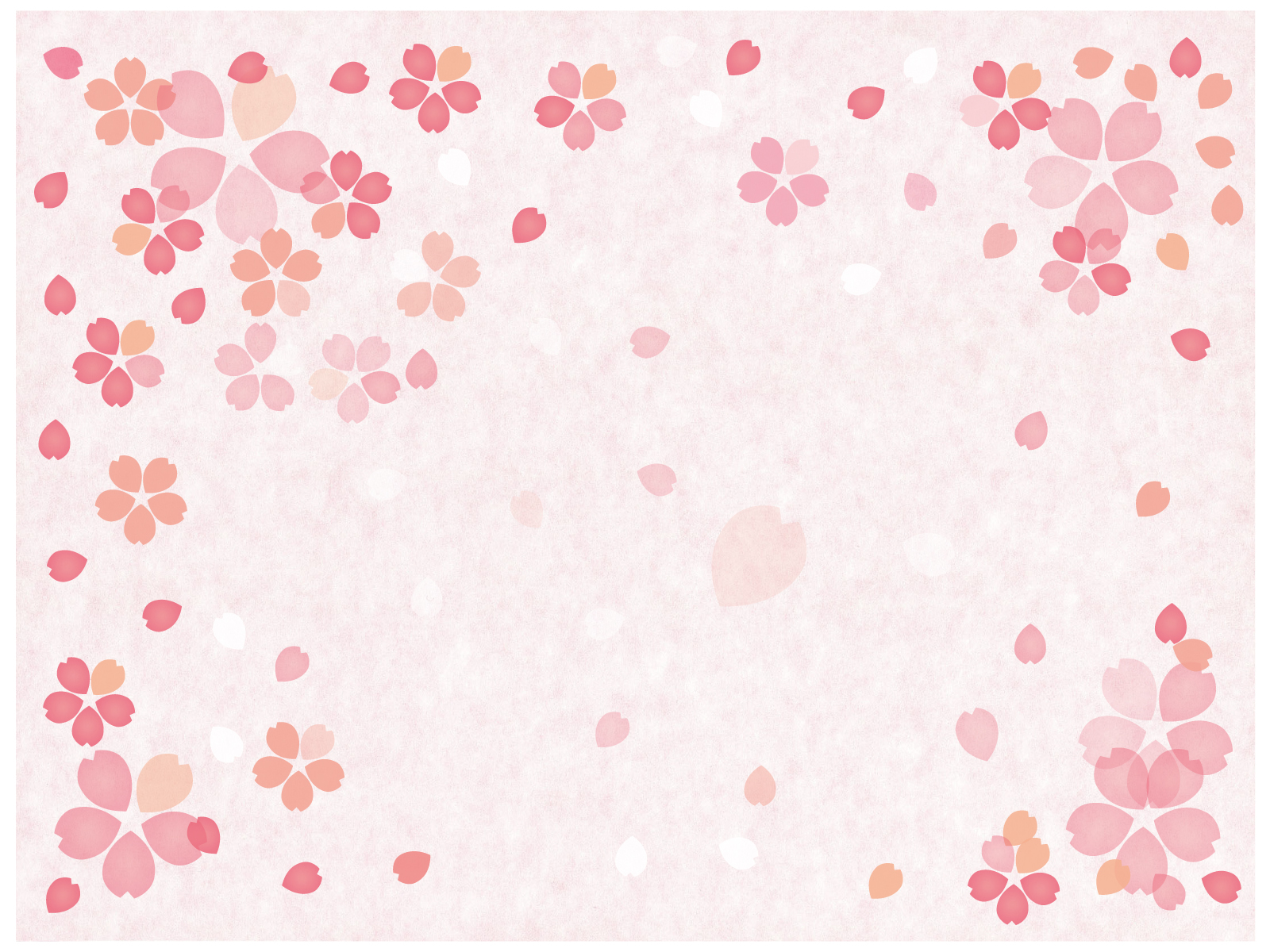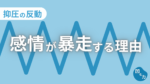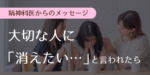こんにちは。国語教師の常田です。
今回で第二部が終わります。最期の源氏の姿から、作者・紫式部の心にも迫ってみたいと思います。
「幻の巻」「雲隠の巻」を解説します。
平成28年、源氏物語千年紀のシンポジウムが京都で開かれた時、一人のご婦人が次のように発言されました。
光源氏のような人物は現実にはいないだろう、という話の後です。
「明治の始めにも、京には光源氏によく似た旦那さんがいらした、と祖母から聞きましたよ。祖母は江戸末期、御所で女官を務めていました」と。
通い所も100カ所、着こなし、身のこなしは誰もが惚れ惚れするようであった、と言われました。
ただ、今となれば、光源氏も「京の旦那さん」も、どちらも夢のようですね。
忘れがたい紫の上の手紙
光源氏(52歳)は、前年に最愛の妻・紫の上を亡くし、季節の移ろいとともに悲しみは深まるばかりでした。
やがて、年も暮れゆく頃となりました。
この一年、出家をためらってきた源氏でしたが、「年が明けたら」と今度こそ覚悟を決めました。
仕える人々に形見の品を与えるなど、本格的に準備を始めます。
後に残しては見苦しい手紙も処分していきますが、他の女性のものとは別にして、今日まで大切にしてきた紫の上の文だけは、捨て難かったのです。
はるか昔にもらったはずなのに、たった今書いたように、墨の痕は鮮やかです。
しかし最後には、「残しても甲斐がない」と女房たちに破らせました。
死出の山 越えにし人を したうとて 跡を見つつも なおまどうかな
(死出の山を越えていってしまった人を追おうとして、彼女の筆の跡を見ながらも、私はいまだ悲しみに暮れ、惑っていることだ)
源氏は、紫の上の筆跡の横に、
かきつめて 見るもかいなし 藻塩草 おなじ雲居の 煙とをなれ
(かき集めたところで、あの人がいないのだから、見る甲斐もない手紙であるよ。亡き人と同じ空へのぼる煙となるがよい)
と書きつけて、あふれる涙とともに全て焼かせたのでした。
光源氏最期の輝き
12月の中頃、恒例の年末の法会が開かれ、源氏が久しぶりに公の場に登場しました。
これが他人に見せた最後の姿であり、彼の生涯で最も美しく光り輝いていたとか…。
六条院で過ごす大晦日、6歳の孫・匂の宮は元気に走り回っています。
出家すれば、もうこのかわいい孫にも会えなくなります。
源氏は耐え難い思いを、この歌に込めました。
もの思うと 過ぐる月日も 知らぬ間に 年も我が世も きょうや尽きぬる
(物思いをして、月日の過ぎるのも知らぬ間に、この一年もわが人生も、今日で終わってしまうのか)
こうして「幻の巻」は締めくくられています。
続く「雲隠の巻」は、巻名のみで本文はありません。
かつては存在したとも、初めから書かれなかったとも、種々の説がありますが、長く寄り添ってきた主人公の最期を、作者・紫式部は書くに忍びなかったのでしょうか。
あるいは、読者一人一人の想像に委ねたのかもしれません。
光源氏の姿は紫式部の投影?
光源氏は、美貌や才能、学問、武芸、政治手腕に音楽やファッションのセンスなど、一切に抜きん出たスーパーヒーローでした。
若き日の恋の狩人ぶりも、彼だから許されたのでしょう。
しかし、肉親の死別や政界追放など、自分に降りかかった災難を他人のせいにして苦しむ、人間くさい姿も描かれています。
若くして仏法に関心を寄せながら、妻子や仕事に執着し、あと一歩踏み出せぬまま晩年を迎え、伴侶亡きあとは坂を転げ落ちるように衰弱していく。その様は、哀れの涙すら誘います。
そんな煩悩の塊の実態は、私たちと何ら変わりません。
源氏の姿は、作者自身の投影ともいわれます。
紫式部もまた、早くから仏法を一筋に求めたいと願いつつ、”晩年を迎えてなお、出家の決断ができないでいる”と日記に吐露しています。
今回で『源氏物語』第二部が終わり、匂の宮をはじめとする光源氏の子・孫の世代が繰り成すドラマ、第三部が幕を開けます。
源氏物語全体のあらすじはこちら
源氏物語の全体像が知りたいという方は、こちらの記事をお読みください。
前の記事を読む 次の記事を読む これまでの連載はコチラ
話題の古典、『歎異抄』
先の見えない今、「本当に大切なものって、一体何?」という誰もがぶつかる疑問にヒントをくれる古典として、『歎異抄』が注目を集めています。
令和3年12月に発売した入門書、『歎異抄ってなんだろう』は、たちまち話題の本に。
ロングセラー『歎異抄をひらく』と合わせて、読者の皆さんから、「心が軽くなった」「生きる力が湧いてきた」という声が続々と届いています!