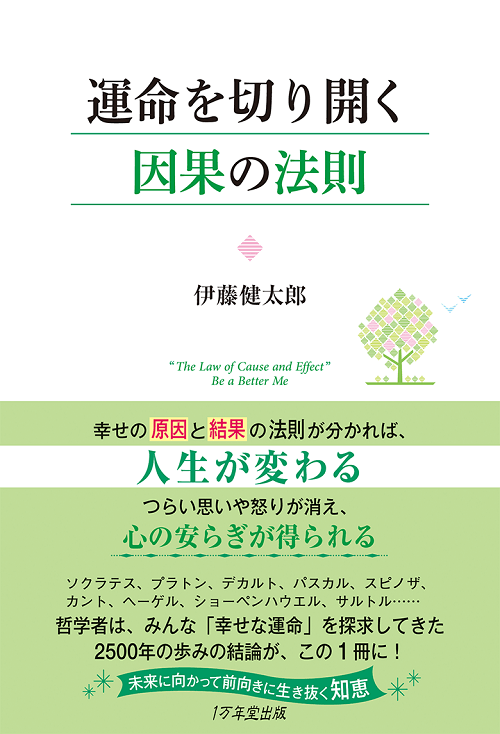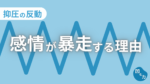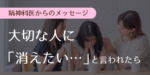平凡な中学生の少女が、大切な「何か」を探すため、遙かなる旅に出る物語。
事故で母親を亡くした知子の前に、ある日突然、ソラと名乗る美しい女性が現れる。
理不尽な運命に心を押しつぶされそうな知子の手を取り、向かった先は――。
運命とは?生きるとは?
現代社会を象徴するかのような、不思議な国々をめぐりながら、その謎に挑戦する冒険が、今、始まる!
第1話 貧しい国編
最近、悪夢をよく見る。
自分の大切な人が死んでしまう夢だ。
母親が車に轢かれ、血を流しながら自分の名前を呼んでいる。
実際にそんなシーンは知らない。だけど、繰り返し見るのでイメージが刷り込まれてしまった。
(あー、もう。早く覚めてよ)
もう、すっかり慣れてしまった夢なので自分でも夢だとわかる。
だが、気分が悪いことには変わりがない。
目覚まし時計が大きな音をたて、少女はうんざりしながら目を覚ました。
(雨か、学校いきたくないな……)
窓の外を眺めてため息をつく。
ただでさえ悪夢で寝ざめが悪いのに、雨がアンニュイな気分に拍車をかける。
彼女は雨が嫌いだ。ぼんやりと窓の外を眺め、意識が覚醒するのを待つ。雨も嫌いだが朝も苦手なのだ。
ほどなくして目覚まし時計が鳴り響き、彼女を現実に引き戻す。
雑に布団をたたみ、ふすまの奥に押し込むと、そのまま着替えもせずにパジャマのままリビングで朝食をとった。
夜勤の父親はまだ寝ているようだ。
(あ、これもうダメだな)
数日前に開封した6個入りのバターロール、最後の1つは変な味がした。裏返したらカビが生えている。梅雨の時期にはありがちなことだ。
(はあ、朝食ぬき。これだから嫌なんだ)
母親がいたときは勝手に食事がでてくるものだと思い込んでいた。
毎食決まった時間に不足のない食事を用意をすることがどれだけ大変か、今になってわかる。
(今さら気づいたって、遅いけどね)
食べかけのバターロールを捨て、自分でいれた緑茶をぐっと飲み干す。
夏のセーラー服に着替え、雑に髪をセットした。
去年の冬からショートカットにしたのだが、セットが楽でいい。
「……行ってきます」
身支度を整え、ぼそっと伝えた相手からの返事はない。
そこには真新しい仏壇と母の遺影があった。
彼女の名前は佐藤知子14才、中学2年。
登校中の学生に混ざれば溶け込んでしまいそうな普通の少女である。
「おはよう、トモ」
仲のよいクラスメートが声をかけてきた。
知子のあだ名はトモ、知子だからトモ。あまりに平凡だ。
「あ、おはよ」
「まだ部活こないの?トモがこなくなってからさ―」
愛想笑いをしながら明るく会話をするが、クラスメートとの言葉も耳に入らない。
(…雨は嫌いだ)
安っぽいビニール傘越しに見る空は暗く嫌な色をしている。
(雨は嫌いだ。嫌なことを思い出すから)
◆◆◆◆◆◆◆
知子の母が死んだ日も、こんな雨の日だった。
ある日、授業中に職員室に呼び出され病院に直行した―それからのことは、正直おぼえがない。
『事故ですって、なんでこんなことに』
『まだお若いのに』
母の死を悲しみ、涙を流す誰かの声。
『相手は焼香にもこないのか』
『スピード違反で信号無視だろ、ただの人殺しじゃないか』
事故の相手をなじり、怒りに震える誰かの声。
『何かあったらいつでも頼っていいのよ』
『まだ知子ちゃんは中学生なのに、こんなことになるなんて』
自分を憐れむ誰かの声。
すべて母の死を悼み、母を喪った自分を気づかってのものだ。それはわかる。
だが、それらの言葉を聞くたびに、人の生の感情が否応なく『母は理不尽な死を迎えた』『私は不幸なんだ』と自覚させ、知子の心を深く深く沈めていく。
そして、あの父の言葉―
『いいかいトモ、相手の学生さんを恨んではいけないよ。これから彼にもつらい人生が待っているだろう。人を恨んではいけない。つらいけど、この運命を受け入れよう』
父親は知子を心配し、自分の悲しみをこらえて諭してくれた。立派な父だと思う。
父の想いは痛いほど伝わった。
(だけど―)
この言葉が、知子の心を深くえぐった。
母は優しい人だった。料理が得意で、陸上競技に打ち込む知子のために日曜日も休まずお弁当を作ってくれていた。
悪いことなんてしてない普通の人が、こんな理不尽な目に遭っていいはずがない。
(真面目に頑張っても、運命でこんな目に遭うなんて…運命ってなんなんだろう)
そう考えるだけで、もうなにもやる気にはならない。
母の死以来、世界が白いカーテン越しに見るようにぼんやりとしている。
それは母の四十九日が済んでも変わらない。
あれほど好きだった陸上部にも顔を出す気にならなかった。
友人も顧問も知子の事情を考えて「休んだほうがいい」と言ってくれたが、それに甘えて顔も出していない。どうしてもやる気になれないのだ。
(どんなに頑張っても、人が起こした事故で死ぬんだ。がんばる意味ってあるのかな?)
こんなこと、誰にも聞けない。
父親や担任など、大人に聞かせたら心配をかけてしまう。
まして友人に相談なんて絶対にできない。こんな話をしたら気味悪がられて孤立してしまうかもしれない。
孤立は女子中学生にとって最も恐ろしいものだ。だから、今でも愛想笑いをし、無理をして話を合わせている。
だが、心は悲鳴を上げていた。わっと声を張り上げて走り出したいような気持ちだった。
◆◆◆◆◆◆◆
大きくため息をつき、傘越しに見上げていた視線を戻す―そこには、見たことのない光景が広がっていた。
見渡す限りの緑。ざっと風にたなびく草原、知子はポツンと1人でたたずんでいた。先ほどまで降っていた雨は気配もない。
(…え、ここ、どこ?)
ぼんやりと周囲を確認するが、どこまで見ても草、草、草ばかりの平原だ。
どことなく、地理の資料集で見たアルゼンチンの牧草地に似ているかもしれない、などと考えていると、強い風が吹きビニール傘が吹き飛ばされてしまった。
傘は見る見るうちに風に流され、小さくなっていく。
「おやおや、今度はずいぶんと若いお客様だね」
不意に、後ろから声がした。
知子は驚き「ひゃっ」と変な声を漏らしてしまう。
「おっと、驚かせたかい?」
振り向くと、そこにいたのは若い、端正な顔立ちの女性だった。
まず驚いたのは背の高さだ。身長158センチの知子より頭ひとつぶんくらい高い…恐らくは180センチを超えているだろう。
声を聞かなければ男性だと思ったかもしれない。
年のころは20代半ばだろうか。
赤い髪を高い位置でポニーテールにし、ゆったりとした肩掛けの上着とズボンを身につけている。
なにより変わったところがあるのは腰から剣のようなものを下げていた。
(モデル?変な格好の外国人だ)
知子は『なんとなくファンタジー小説にでも出てきそうな恰好だな』などと見当違いのことを考えてしまうが現実逃避以外のなにものでもない。
衝撃が強すぎて固まってしまった知子を見て、彼女はクスリと笑みを見せた。
「あ、アイキャントイングリッシュ―」
「ここはね、行き場をなくした迷い子の隠れ家。自分を見失った者たちの最後の止まり木」
なにやら難しいことを言っているが日本語だ。これには少しほっとした。
思い返してみれば女性は初めから日本語で話していた気がする。なんだか恥ずかしくなってきた。
「ふうん、なんだかぼんやりした子だねえ。まあいい、アタシはいまからアンタを案内するソラだよ」
「案内?その…ソラ、さんはどこかに連れてってくれるんですか?」
当たり前だが、知子とて見知らぬ外人にホイホイとついていくほど馬鹿ではない。
だが、 知らない土地に知らない外国人、知子は『これは夢だ』と納得しかけていた。
そもそも、通学中にいきなり草原にきたのだ。現実ならば大変なことである。
夢だと思えば少し気が楽になった。
「アタシのことはソラでいいよ。それから、勘違いしているようだけどアタシがアンタをどこかに連れていくわけじゃない。
迷子のアンタはこの世界を旅して何かを見つけなきゃいけないのさ。それまで不慣れな世界を案内するのがアタシってわけ」
よく分からないが、このソラは知子の助けをしてくれるらしい。
しかし『何かを見つける』とはなんであろうか。またわからないことが増えた。
「ソラ、何かってなに?」
知子は馴れ馴れしく話かけるが、これは夢だと信じ込んでいるためだ。
本来の彼女は年相応に人見知りもする内向的な少女である。
「知らないね。アタシはアンタじゃないからね。答えは自分で見つけるものさ。それより、いい加減に名前を教えな。いつまでもアンタじゃ呼びづらいからね」
ここで知子は自己紹介すらまだであったことに気がついた。
(私の夢のくせに私のことを知らないなんて)
なんだかおかしくなり、クスリと笑みがこぼれた。

「私は知子、佐藤知子よ。よろしくね、ソラ」
それだけ告げると、知子はソラと握手をした。思ったより固い手のひらだ。
「トモコ、サトウトモコね。ちょっと難しいからトモって呼ばせてもらうわ」
ここでもやっぱりトモだ。知子はこれで『やっぱり夢だ』と確信した。
さすがに見ず知らずの外人まで同級生と同じあだ名をつけるとは思わなかったからだ。
こうして、知子の奇妙な旅が始まる。旅の中で、彼女は『何か』を見つけることができるのだろうか―
◆◆◆◆◆◆◆
旅は、ろくにキャンプもしたことがない知子にとって驚きの連続である。
どこからともなく食料を集めるソラに感心し、彼女が捕らえてきたウサギの解体にショックを受けた。
同じ服を着続ける不快感はあったが、冷たい流れでの水浴びも新鮮な喜びで満ちていた。
つまり、ソラとの旅は、知子にとって楽しいものであったのだ。
ぶっきらぼうで粗野なところのあるソラではあったが、知子を気づかう優しさがある。
今でもさりげなく、歩く速度を合わせてくれているのを知子は気づいていた。
(こんなのも、いいかもね)
いつの間にか知子は、この非日常を楽しんでいる自分に気がついた。
歩きづめのキツさはあるが、ここには気詰まりだった人間関係はない。
知子は奇妙な解放感と安らぎを覚えていたのだ。
「ソラ、この先はどこに行くの?」
「ああ、この道は『貧しい国』だね」
ソラは知子の様子を見て「治安も悪いし、サッと通りすぎるのがいいかもしれないね」と苦笑する。
だが、この言葉を聞いても知子にはピンと来ない。
わからないまま適当に「ふうん、そうなんだ」と相づちをうつ。
そんな態度にソラは何か言いたげであったが「まあ、いいさ」と何かを納得したようだ。
「驚いても大声を出して注目を集めたり、1人にならないこと。どんなつまらない用事でもアタシに声をかけるんだよ」
「うん、そうする」
ソラは軽くため息をつくが、ここが『夢の世界』だと思い込んでいる知子にソラの忠告は耳に入らない。
日本で中学生をしていた彼女にとって、貧しさとはユニセフのポスターの中、どこか遠くの世界のことだった。
しばらく行くと人家がまばらに増え、2メートルほどの高さを備えた壁が見えてきた。これがソラの言う国だ。
門番らしき兵隊とソラが少しやり取りをし、少し硬貨を手渡したようだ。
「今のはなに?」
「入市税さ。無いとこもあるけど、この町はある」
ソラの説明はわかるようでよくわからない。
知子は「ふうん」と気のない返事をし、門を潜った。
(うっ、これ…なに?)
そこに広がる光景に知子は怯んだ。だらしなく道端に座り込む汚ならしい浮浪者たち、まとわりつく不快な臭いは公衆トイレのそれに似ている。
目の前の光景に知子は怖じ気づいた。
「てめえ、ショバ代もなしとはいい度胸してやがるな!このナーラさまに逆らう気か!!」
「誰に断って商売してやがるんだ!」
どこからともなく怒声が響き、知子は反射的に首をすくめた。
見れば小太りの男が率いるガラの悪そうな男たちが露店をメチャクチャに荒らしている。
「驚いたかい?どこの町でも日陰になりやすい城壁の近くは貧しい市民が集まりやすいもんだけどね、ここは特別さ」
ソラは歩きながら「見てごらん」と商店を示す。
そこには警備員らしき屈強な男が鉄格子のようなドアを守っていた。
「この国はね、皆が欲のまま好き放題にしてもいいと思ってる国なんだ」
ソラが低い声でぼそぼそと話す内容に知子は衝撃を受けた。
ついキョロキョロと周りを窺ってしまうが、ソラに「目立つ真似をするな」と低く叱られる。
おそらく目立たないように低い声で話してるのだと知子は気づき、小さく頷いた。
「警察はいないの?」
「いるにはいるけどね、この国では罪は金で購える。この町を取り仕切る親分のカレスがそう決めたからね」
知子は目まいがした。この国の常識は理解の範疇を越えている。
(そんなメチャクチャな国があるの!?悪いことし放題だよ!)
知子は海外旅行すらしたことがない。カルチャーショックで頭が真っ白だ。
「はじめはね、人生をやり直せる、再起ができる国にしたかったらしい。他で過ちを犯しても、ここで真面目に働き、決められた罰金を払えばリトライできる。そんな国にね」
ソラの言葉は難しいがピンとくるものがあった。
知子はテレビで犯罪者の社会復帰を追ったドキュメントを見たことがある。一度きりの過ちを犯した若者が『犯罪者』というレッテルに苦しむ内容だ。
番組を見たときはずいぶん同情したのを覚えている。
そのことを伝えると「そうだね、この国の問題は許しの基準を金にしたことさ」とソラは苦い顔をした。
「人は弱い。法律を守る者がいなくなるのに時間はかからなかったよ。何をしても金を払えば許される。罰がないのに自分を正しく保つのは難しいからね」
ソラは寂しげに笑い「だからここは貧しい国なのさ」と呟いた。
「貧しい国?お金持ちがやりたい放題できるのに?」
「そうさ、貧乏人も金持ちも誰もが騙されないように虚勢を張り、周囲に怯えて暮らしている。心根の貧しい人々が住まう国さ」
知子にはわかるような、わからないような話だ。
「さっきのナーラなんてのは学も人徳もないゴロツキさ。だけど金があって声の大きなヤツが偉くなる。そんなつまらない国にしちまったのさ。カレスってのは」
ソラの口調は鋭さを増していく。
混乱する知子はスキだらけだったのだろう、突然ソラが「おっと、この子はツレでね」と知子を庇うように動いた。
驚いて身をすくめると、物乞いらしき老人が鋭く舌打ちする。
ゾッとした。どうやら知子のスクールバッグに手を伸ばしていたらしい。
「ぼやぼやして物を盗られても『盗られたほうが悪い』って国さ。気をつけるんだよ」
恐怖で身を縮める知子にソラは優しく語りかける。まるっきり子供扱いだ。
「ま、少しずつ見ていけばいいさ。あとは…そうだね、その格好は目立つ。少し買い物でもするかい?」
◆◆◆◆◆◆◆
言うが早いか、ソラが入ったのは良くわからないものがごちゃごちゃと並んだ薄暗い店だった。
ソラは店主になにやら注文しているが、サイズなどを確認しているところから察するに、知子の服のようだ。
確かにセーラー服はこの町では浮いている。目立たない服に着替えるのだろう。
ソラが選んだのは、だぼっとした厚手のシャツとズボン。腰にはウェストポーチに似た大きな雑嚢と刃渡り15センチくらいのナイフ、それに水筒。
マントのような肩掛けの上着にはフードもついていた。スクールバッグは肩からかける。

「ま、そんなもんだね。少しばかり軽装だけど、一般的な旅人の格好さ」
ソラは知子の姿を見てニヤリと笑う。
「今までの服もとっておくんだよ。自分が誰なのか忘れないためにね」
また、わかるようなわからないような話だ。だが、知子は素直に「わかった」と制服を小さくたたみ、雑嚢の底にしまった。
「本当にトモは行儀がいいね。やることなすことに品がある」
「そうかな?たしかにソラはワイルドすぎかも」
知子には分からないが、このソラの言う『行儀のよさ』とは平成や令和の日本人が持つ特徴であろう。
一種の規範意識が骨の髄までしみ込んでおり、自らが枠からはみ出ることを異常に恐れ、他人の失言や過ちにも敏感だ。
この現代人の雰囲気が、ソラにとっては『品があり』『ぼんやりしている』ように見えるのかもしれない。
そんなことは露知らず、二人は軽口を言い合いながら、他の雑貨(?)を見て回った。
「これは火打ち石さ。こうやって鉄にぶつけると火花が出る。こっちの手ぬぐいは止血にもつかえるし、旅にはなにかと便利だね」
「火打ち石?石と石をぶつけるんじゃないの?」
初めて見るものばかりの知子はいちいち感心し、ソラや店主が「なんて世間知らずだ」と呆れる――こんなやりとりを数十分続けたころ、異変は起きた。
◆◆◆◆◆◆◆
「――ッ!――の――やろう!!」
「お前が――を――してやる!」
凄まじい罵声と、何かをぶつけるような音が店の外から響く。争いの気配だ。
たったこれだけのことで知子は体がすくむ。
争いなどクラスメートのケンカくらいしか見たことがない。
店の外から聞こえる怒声は彼女の肝を冷やすのに十分な迫力があったのだ。
「大丈夫、さすがに店のなかには入らないよ」
ソラが「あの兄さんが守ってくれるさ」と警備員に目配せをすると、愛想のない男が警棒をわざとらしくカチャリと鳴らした。
店主にも、うろたえた様子はない。
(ひょっとして、よくあることなのかな?)
知子は周囲の落ち着きぶりを見て、そんなのごめんだとため息をついた。
時間にしたら30分ほどだろうか、知子にとっては長い時が過ぎた。
「外の騒ぎが治まったね。ちょいと見てくるからここにいるんだよ」
ソラは返事も聞かずに分厚いドアから出ていく。
(え?ここで放置…?)
さすがに争い事があった表に出るのも気が引けるが、店の中で放置されるのも気まずいものがある。
なにせ知子が身につけているものの支払いはまだ済んでいないのだ。
落ち着かない気持ちで待つことしばし、ソラが戻ってきた。
怪我人に肩を貸しているようだ。
「ちょいと怪我人がいたんでね。店の隅を貸しとくれ、それと水だ」
ソラは硬貨を2枚、店主に放り投げて怪我人を椅子に座らせる。
怪我人は頭と口から血を流し、意識が朦朧としているようだ。
「トモ、怪我の手当ては旅に役立つ、見て覚えな」
「でも、血が…」
どれだけの暴力を受けたらここまで血が流れるのか想像もできない。
知子は立て続けに起きる出来事でパニックになっていた。
「血ぐらいなんだい!ここで憶えなきゃ次に誰かが死ぬかもしれないよ!しっかり見て憶えなっ!」
ソラは知子を一喝し、店主が持ってきた手桶の水で手ぬぐいを浸して血まみれになった顔を清めていく。
そして、清められた怪我人の顔を見た知子は「あっ」と声を出した。
それは先ほど、知子からスクールバッグを盗もうとした老人だったのだ。
「…ソラ、この人さっきの泥棒だよ」
「知ってるよ、コイツはさっきも人のものを盗もうとして袋叩きにされたのさ。
でも、血を止めなくちゃ死ぬかもしれない。死ななくても手当てがなけりゃ不自由するかもしれない。
泥棒がなんだ、それがコイツを助けない理由になるのかい」
おそらくソラの言葉は正しいのだろう。彼女には迷いがまるでない。
(…でも、悪い人を助けたらまた誰かのものを盗むかも)
知子の迷いを知ってか知らずか、店主も「奇特なことだ」と肩をすくめた。
「歯が折れてる、これはどうしようもないね。だけど頭の怪我は浅手だよ。頭は血が出やすいんだ」
ソラは怪我人に容態を説明しているようだ。意識の有無を確認しているのかもしれない。
「…っぐ、やめろ。金なんか持ってねえぞ」
「知ってるよ、だから医者じゃなくてアタシが診てるんだよ。肩が抜けてる、ちょいと痛むが突っ込むよ」
ソラが思い切り怪我人の右腕を引っ張ると、痛みに耐えかねた怪我人は「ぎゃああ!」と絶叫を上げた。
もう見ていられない。
「しっかりしなよ!あとは腕を吊れば大丈夫だ」
ソラは新しい手ぬぐいを裂いて紐を作り、怪我人の腕を固定した。
知子の持っている治療のイメージよりは少々乱暴だが、見事な手際だ。
◆◆◆◆◆◆◆
「…トモ、泥棒は悪いことだ。盗みをなすなら悪人と言っても良いだろう。なら、いい人ってなんだろうね?」
治療が一息ついたのだろう。ソラが振り返り、知子に問いかけた。
いままでの切迫した雰囲気はもう影を潜めている。
「いいナイフは丈夫でよく切れるナイフさ。いい火打ち石はすり減らずに火花を散らす石だ。じゃあ、いい人間は?」
ソラの問いかけは難しい。知子には何も答えることができない。
「いい人間はね、よく生きる人間さ。ただ生きているのではなくてね」
「…よく、生きる?」
ソラは「そうだよ」と優しく微笑む。
「罰を受けないからって悪いことをしてもいいわけじゃない。泥棒を続けた結果、こんな年になって半殺しにされる。悪い種からは悪い芽がでて悪い実をつけるもんさ」
「それはわかる、けど―」
知子にもソラの言葉の正しさはわかる。だが、どうしても納得のできない部分もある。
(母さんは悪いことなんてしてないっ!絶対に)
悪い行いが悪い結果を生む、その正しさはわかる。
だが、それを認められない自分もいる。
でも、それを口にすることが怖かった。
この夢の中でソラから見捨てられたら…想像するだけで震えがきそうだ。
「この国じゃな、そんな理屈は通用しないぜ」
ポツリと怪我人が呟いた。
折れた歯が痛むのか、少し聞き取りづらい声色だ。
「強い奴が弱い奴から奪うのが道理よ。俺を見ろ。間抜けから奪い、それを奪われる…これが日常、当り前さ」
ソラは老人の言葉を遮るでもなく、じっと耳を傾けていた。そして、老人の言葉を反芻するように「奪うから奪われるんだね」と頷いた。
「なら奪うのをやめて与えてみな。奪うから奪われる、なら与えるなら与えられるかもしれない。荒んだ常識を変えたければ自分から変わることだ。
この世界は『よく生きるもの』に微笑むだろう。正直者は馬鹿を見るなんてのは正直に生きていないやつの戯言さ」
噛んで含めるようなソラの言葉は穏やかだが力強い。
ひょっとしたら自分に聞かせているのかもしれないと知子は感じた。
(ソラの言葉は正しいよ、でも―)
どこかで『泥棒の言うことが正しい』と感じている自分がいる。
人を信じられない自分がいるのだ。
そんな知子の様子を見たソラは「いいさ」と笑う。
「これはアタシの答えだ。アンタの答えはどこの本にも書いてないし、どこかの賢者が教えてくれるわけじゃない」
ソラはポンと知子の頭に手を置いた。
「自分で考えるのさ。トモは旅の中でトモの答えを見つけるんだ。目と耳と、頭を使ってね」
知子は頷くことしかできない。14才の身ではソラの言葉はどんな勉強よりも難しく感じた。
「アンタもだよ。やり直すのに今日より早い日はない。腕を痛めたのはいい機会さ、これに懲りて泥棒は辞めることだね」
ソラは怪我をしている泥棒に声をかけ「アッハッハ」と豪快に笑う。すると泥棒はばつが悪そうにそっぽを向いた。
(自分で見つける、か)
それは今まで与えられるだけだった知子にとって、初めての言葉だったかもしれない。
(いい人間は、よく生きる人…じゃあ『よく生きる』ってなんだろう?)
これは、知子の心に生まれたはじめの問い―この答えは、自分で見つけるしかない。
「さあ、長居はせずに次の国に向かうよ」
悩む知子の背中を、ソラがバンと叩いた。
小説の続きを読む
新連載を読みたい方は、ぜひ以下のLINEにご登録ください。
ココロほっとLINEへの登録はこちら